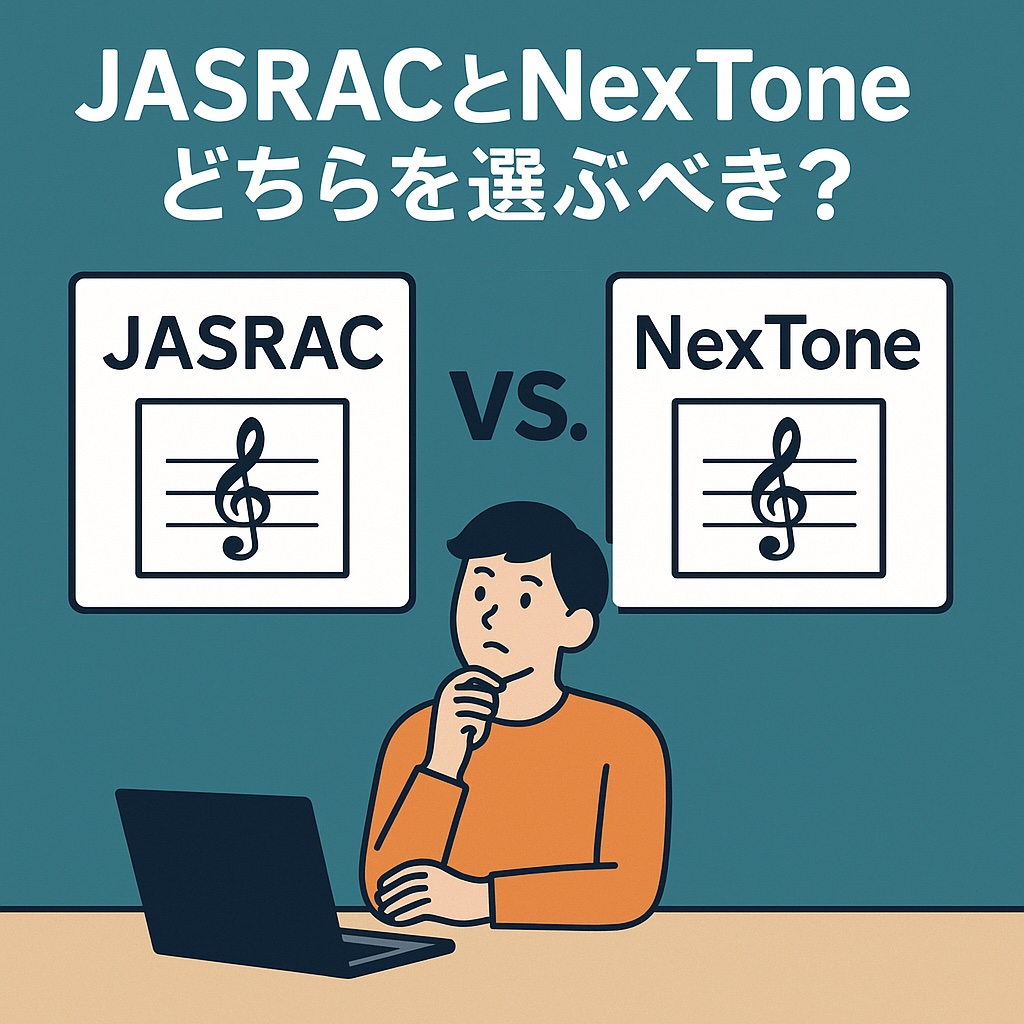インディーズで音楽活動をしていると、「自分の曲の著作権はどう管理すべきか?」という疑問が出てきます。
日本には JASRAC と NexTone という2つの主要な著作権管理団体があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。
本記事では、著作権管理団体とは何かという基礎から、JASRACとNexToneの違い、登録する利点・欠点、判断のポイント、そして Frekul(フリクル)を活用した柔軟な方法まで、独立系音楽アーティストの視点で丁寧に解説します。
正確な情報に基づき、自分の活動スタイルに合った選択ができるよう一緒に見ていきましょう。
著作権管理団体とは?音楽家が知っておくべき基礎知識
まず、「著作権管理団体」とは何かを押さえておきましょう。
著作権管理団体とは、作詞者・作曲者などの著作権者に代わって、音楽作品のライセンス供与や利用状況の監視、使用料の徴収・分配を行う組織です。
具体的には、楽曲を利用したい第三者(例えば放送局や配信サービス、ライブ主催者など)に利用を許可し、定められた著作権使用料(ロイヤリティ)を徴収して、権利者に分配する役割を担っています。
音楽家は、大きく分けて 自分で著作権を管理する方法 と、専門の団体に管理を委託する方法 があります。
自分で管理する場合、曲を使いたい人との個別交渉や、無断利用されていないかの監視、使用料の回収まで全て自力で行わなければなりません。
これは相当な労力であり、全国で自分の曲がどう使われているか把握するのは現実的に困難です。
そこで多くの作家は、JASRACやNexToneといった著作権管理団体に自分の楽曲の管理を委託します。
団体に委託すると、ラジオやテレビ、コンサート会場、さらにはカラオケやインターネット上まで、全国的に楽曲の利用を監視・管理してもらえます。
利用者(曲を使いたい人)は、その曲が管理団体の 管理楽曲 であれば団体から包括的に許諾を得て使用料を支払えば良く、管理されていない曲(=権利者が自主管理している曲)の場合は直接権利者とやりとりする必要があります。
日本国内の楽曲のほとんどは、主要な2団体(一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC と 株式会社NexTone)のいずれかで管理されています。
したがって、あなたの曲を他人が使いたい場合、JASRACかNexToneに信託されているかどうかで対応方法が変わるわけです。
JASRACとNexToneの違いとは?
では、日本の二大著作権管理団体である JASRAC と NexTone にはどのような違いがあるのでしょうか。
両者とも音楽著作権の管理事業者ですが、設立の経緯や組織形態、管理の範囲や方針にいくつか違いがあります。
組織の成り立ちと目的
- JASRAC は1939年設立の歴史ある団体(一般社団法人)で、長年日本の音楽著作権管理を独占的に担ってきました。
- NexTone は2000年代に入ってから新規参入した民間企業2社(イーライセンス社とジャパン・ライツ・クリアランス社)が2016年に統合して生まれた比較的新しい株式会社です。
背景には、JASRACの独占や硬直的運用への音楽業界内の不満があり、より柔軟で権利者の意向を反映できる管理を目指してNexToneが登場した経緯があります。
JASRACが非営利の社団法人として「文化の発展」を目的に掲げるのに対し、NexToneは営利企業として「権利者の利益向上」と業界の新時代のニーズに応えることを掲げています。
この違いは後述する国際ネットワークや信頼性にも影響しています。
(※JASRACは世界的な管理団体連合であるCISACのメンバーですが、NexToneは営利企業のため加盟できません)
管理対象(扱う媒体・サービス)の違い
基本的にJASRACもNexToneも、音楽の演奏権・録音権・配信権などあらゆる利用形態を管理可能です。
ただし実際の運用には差がありました。
- JASRAC は従来すべての利用形態(テレビ・ラジオ放送、コンサート、BGM、通信カラオケ、配信、CD/DVD化、出版など)を網羅的に管理しています。
- 一方、NexTone はサービス開始当初、主にCD録音やインターネット配信など一部の分野から管理を始め、徐々に管理範囲を拡大してきた経緯があります。
例えばNexToneは2000年代半ばに放送や通信カラオケの管理にも参入し、最近では2022年4月から一部の演奏権(演奏会等の利用)についても著作権料の徴収を開始しました。
とはいえ2025年現在でも、生演奏や小規模な演奏利用についてはJASRACが強い分野で、NexToneはまだシェアが小さい状況です。
そのため、例えばあなたの曲がライブハウスで演奏された場合、NexTone管理曲だと会場側が対応に戸惑うケースもあるかもしれません。
逆に、配信やYouTubeなどインターネット領域ではNexToneも積極的で、Google社(YouTube)とは早期に包括契約を結ぶなどデジタル分野の実績があります。
要するに、JASRACはオールラウンドに伝統的な媒体を網羅、NexToneはデジタル時代に合わせ柔軟に拡大中と捉えると良いでしょう。
登録することのメリットとデメリット
著作権管理団体への登録(信託/委託)には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
ここでは音楽家にとってのメリット・デメリットを整理します。
メリット
- 使用料の確実な回収と分配 自分では把握できない全国のカラオケ店や放送局、ライブ施設、ネット配信などからも使用料が集められるため、機会損失が減ります。
- 許諾や管理の手間を省ける 許諾・監視・契約処理をすべて団体が行ってくれるため、本業の音楽活動に専念できます。
- 音楽利用者にとって使いやすくなる 管理団体に登録されていることで、第三者があなたの楽曲を使いやすくなり、利用機会の増加につながります。
- 国際的な徴収ネットワーク 特にJASRACは海外団体と連携し、国外の著作権使用料を回収できる体制を持っています。
デメリット
- 自由な無償提供が難しくなる 自作曲でも例えばXに音源を投稿したり、自分の公式サイトに歌詞を掲載するには許諾が必要になります。
- 信託範囲の制限 原則として契約中は特定利用形態の除外が難しく、柔軟な対応がしにくくなります。
- 自己利用にも費用がかかる可能性 自作CDプレスや自演奏でも手続きや費用が発生するケースがあります。
- 契約のハードル 一定の公表実績が求められ、無条件で登録できるわけではありません。
登録すべきか?判断のポイント
著作権管理団体に楽曲を預けるべきかどうかは、以下のような要素を踏まえて判断しましょう。
- 楽曲の利用予定範囲・収益化チャネル CD流通やテレビ・ラジオ放送、配信、カラオケなど幅広く利用される可能性があるなら登録がおすすめです。
- 楽曲を他者に使ってほしいか、自分で完結させたいか 利用を広げたいなら登録、自分だけで管理したいなら自主管理が合っています。
- フリー配布や二次創作を許容したいか 自由な配布やファンによる二次創作を重視する場合、管理団体への登録は慎重に考える必要があります。
- 国外展開や将来の展望 海外展開を目指すならJASRACの国際ネットワークを活かす選択もあり得ます。
- 管理の手間とコスト 手間を省いて収益化したいなら登録が有効。すべて自分で対応するならコストゼロで管理可能です。
登録方法の紹介(JASRAC / NexTone)
著作権管理団体に楽曲を登録するには、いくつかの方法があります。
ここでは JASRAC と NexTone の登録方法について、それぞれの特徴や手順を解説し、さらに 音楽出版社経由での登録 という別のルートについても触れていきます。
JASRAC
- 個人(著作者本人)として信託契約を結ぶ場合:JASRACでは、作詞家・作曲家などの著作者本人が直接信託契約を結ぶことができます。契約には以下の条件があります:
- 過去1年以内に他者により楽曲が公表・使用された実績があること
- 契約申込金:27,000円(税込)
- 必要書類(本人確認書類、作品リストなど)を提出
- 音楽出版社経由で登録する場合:著作者が音楽出版社と契約を結び、その出版社が JASRAC に登録申請を行う方法もあります。この場合、信託契約自体は出版社名義で行われるため、著作者は申込金や直接の書類提出を省略できることがあります。音楽出版社は印税の一部を取得しますが、代行業務を行ってくれるため、初めて登録する人にとってはハードルが低くなる場合があります。
NexTone
- 個人(権利者)として委託契約を結ぶ場合:NexToneでは、一定の実績を持つ著作者が直接委託契約を結ぶことができます。条件には:
- 直近1年以内の公表実績(例:YouTube5万再生、カラオケ配信、全国流通CDなど)
- オンラインでの事前審査申請(10営業日程度)
- 契約費用は無料
- 音楽出版社を通じて登録する場合:NexToneでは、元々音楽出版社を通じて契約する方式が主流でした。現在も、著作者が個人ではなく音楽出版社と契約し、その出版社がまとめて楽曲を委託登録する形が多く採用されています。特に実績が少ないアーティストでも、出版社が代理人となって契約を進めることで登録のハードルが下がります。
Frekulを使うという選択肢
独立系アーティストにとっては、JASRACやNexToneに直接契約する以外に、Frekul(フリクル) を通じて著作権管理を行うという方法もあります。
Frekulは音楽出版社としての機能を持っており、あなたが希望すれば Frekulが音楽出版社としてNexToneとの契約を代行することが可能です。
特に「NexToneに直接申し込みをするには公表実績が足りない」という場合でも、Frekulを通じて契約することで条件を満たせるケースがあります。
また、Frekulの カラオケ配信サービス を利用すれば、
- 楽曲をJOYSOUNDで配信できる
- 放送・通信カラオケの利用に関してのみNexToneに著作権管理を委託できる
- それ以外の利用(YouTube、ライブ演奏、配信など)は自主管理のままにできる
という柔軟な運用が可能になります。
これにより、
- 印税収入の獲得(カラオケで歌われた分)
- 自由なプロモーション展開(ネット上での無料公開や配信)
を両立させることができます。
Frekulを通じた信託・委託契約には追加の費用(例:1曲あたり約5000円)がありますが、初心者にもわかりやすく、フォーム入力と必要素材の提出で申し込める手軽さがあります。
まとめると、Frekulを利用すれば「カラオケ配信から印税収入を得たいけど、全体を信託するのは避けたい」というアーティストに最適な選択肢となります。
まとめ:JASRACとNexTone、あなたはどちらを選ぶべきか?
- 商業的な展開や海外利用も見据えるなら JASRAC
- デジタル配信中心で柔軟な管理を望むなら NexTone
- まずはカラオケ配信から印税を得たいなら Frekulの活用 がおすすめ
いずれにせよ、著作権管理団体への登録は音楽活動が本格化した段階で検討するのがベストです。
あなた自身の音楽活動の規模やスタイルに合わせて、最適なパートナーを選びましょう。
参考リンク: